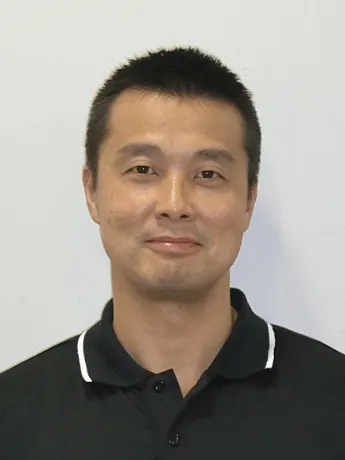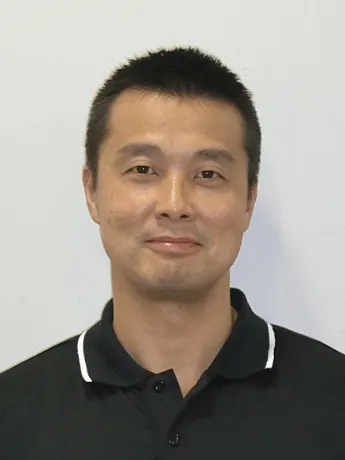理念・発足

相互研鑽を通じて専門性を高め、それにより社会への貢献を果たすことを目指して集う組織です。
JATIの活動の方向性
1.
全世界から情報を収集し、日本に適合したトレーニング法や指導法、システム等について会員間で情報交換を行い、より良いものを追求することを目指します。
日本の環境や実状に合った
トレーニングの構築2.
国内のトレーニング指導者にとって本当に役立つスタンダードな資格の構築を目指します。
日本における
トレーニング指導者資格の確立3.
トレーニング指導者の雇用促進、待遇改善、行動規範や倫理規定の策定などを通じて、社会的地位の向上を目指します。
トレーニング指導者の
社会的地位の向上と相互扶助4.
トレーニング指導者を目指す人を対象とした教育、専門家としてすでに現場で活動している人を対象とした研修や情報交換、会員間の交流などを通じて、互いに向上することを目指します。
教育・研修、指導者間の
交流や情報交換の促進
JATI会員と
JATI限定資格保有者のメリット
1.
JATIは、今後オフィシャルサイト等を通じて、会員及び認定資格保有者に対して、最新の科学的知見やトレーニング法、求人などの情報提供を積極的に行います。また、競技スポーツやフィットネスに関連する各種団体への働きかけや連携を通じて、職域開拓を推進します。
活動機会の増大2.
JATIは、会員や認定資格保有者の優位性に関する広報活動に力を入れます。これによって、将来、就職や活動の機会の増大、待遇改善などが期待されます。
有益な情報の提供3.
JATIは、会員及び有資格者を対象とした物品の割引購入、損害保険の団体加入などの特典の増大を図ります。
会員・有資格者の特典の増大
発足の経緯
そのような人たちが、常に研鑽を積み、専門職としての知識と技能を高めるべく、お互いに交流を拡げ、情報交換や議論を深める場を作りたいという機運が高まり、この会の発足に至りました。
2005年12月23日、名古屋に集った11名が会の発足の意思を固めました。その後、趣旨に賛同した5名を加えた16名を発起人に、2006年4月15日京都において、任意団体としての創立を迎えました。
そして2006年8月7日に特定非営利活動法人の申請が承認され、8月21日に、正式に特定非営利活動法人として設立されました。
初代理事長祝辞
『体力』、あるいはこれに類する言葉がいつの頃から登場したのか定かではありませんが、私の知る限りでは明治30年頃に、欧米人に較べて日本人の筋力・パワーが弱いと指摘した文章があります。講道館創始者嘉納治五郎氏が記した、大要次のようなものです。『欧洲の兵士は大砲を3人で操作できるのに、わが国の兵士は5人必要とする』つまりわが国の兵士の筋力・パワーが欧洲の兵士の6割しかない、というわけです。
そういえば同氏が書いた別の文章の中にも、わが国のオリンピック出場選手が体力的に劣勢にある、と記されていたように思います。日本選手の体力不足は、その後のオリンピック参加ごとに反省として語りつがれてきました。
これの改善に日本体育協会が敢然と取り組んだのは昭和39年の第18回東京オリンピックを目指したときのことでした。 Circuit Training や Weight Training、Isometrics が普及していったのはこのときからでした。これらに続いて Interval Training や Fartlek などの持久力養成トレーニングが、また柔軟性養成の Stretching が広まっていきました。
語呂合せが好きな私は、かねてから体力を"Strength(筋力)"、"Stamina(持久力)"、"Suppleness(柔軟性)"の3要素を上げて、それぞれの頭文字を取り上げ『体力の3"S"』と呼んできました。
当然のことですが、これらの各要素はそれぞれ独自の発展の歴史をもっています。しかしスポーツ競技の分野はいうに及ばず、高齢化が進み、体力づくり・健康づくりに多くの人が関心を寄せる今は、体力・健康づくりの専門家が一堂に会して、それぞれの専門知識を披瀝しあうことは大きな意味があることと思います。
これまで体力トレーニングは外国からもち込まれたものが多かったように思われますが、いまこそ日本発の体力・健康トレーニング法が誕生してもよいのではないでしょうか。一つ皆様方の力を合せて、本協会の会員になってよかったと思われるような立派な団体に育て上げようではありませんか。
2006年5月31日
日本トレーニング指導者協会理事長 窪田登(執筆当時)